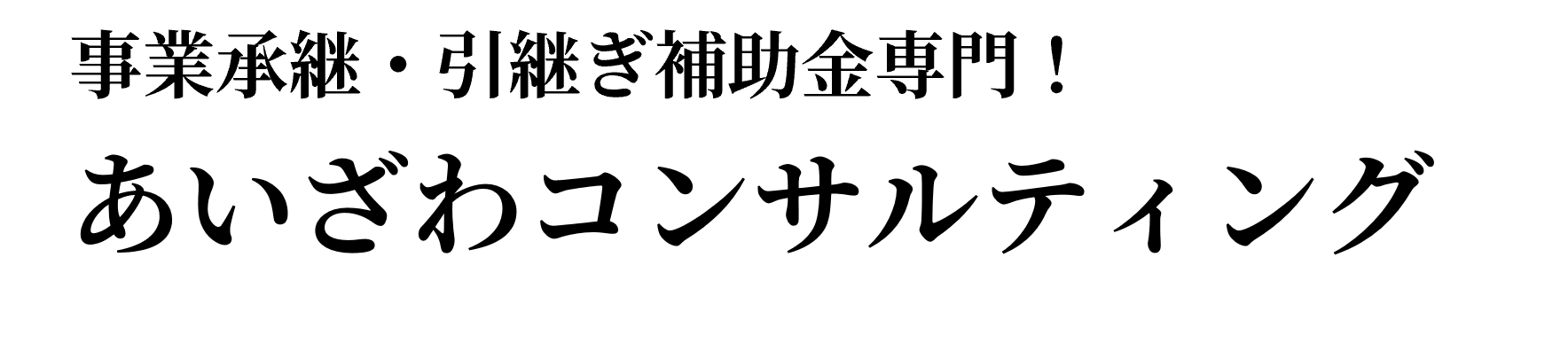いつもお世話になっております。あいざわコンサルティング、中小企業診断士の相澤和彦です。
現在、事業再構築補助金13回の公募が始まっています。事業再構築補助金は、11回から採択率が大幅に低下し、12回も採択率が大幅に向上することはありませんでした。私も、事業再構築補助金10回までは100%の採択率を誇りましたが、11回からは初の不採択もあり、苦しい戦いが続いています。12回も厳しい採択率で厳しい戦いとなりましたが、その中でも採択された事業者様の事業計画書のAI分析をしてみました。
以下、AI分析です。
採択された理由を、審査項目ごとにさらに具体的に分析します。
(1)補助対象事業としての適格性
- 付加価値額の成長率
- 本事業計画では、5年間で付加価値額の年平均成長率が○○%と試算されています。これは、審査基準の「年平均成長率3.0%~4.0%以上」を大幅に上回り、補助事業としての適格性が明確に満たされています。
- 審査基準に求められる具体的な成長目標(付加価値額や利益率)が計画書内で数値化されており、評価されたポイントです。
- 事業再構築指針に基づく取組み
- 本事業は○○支援を対象としており、ポストコロナの社会変化に対応した内容です。特に、地域社会と○○をつなぐプラットフォーム構築という新たな挑戦が「事業再構築」の意義に沿っています。
(2)新規事業の有望度
- 市場性と規模
- ○○市場は、競争が少ないニッチ市場であり、成長性が見込まれると分析されています。
- ターゲット市場の具体的な規模やニーズがデータに基づいて説明されており、審査員に説得力を与えました。
- 参入可能性と競合分析
- ○○対応のオンラインプラットフォームを構築することで、他社との差別化が明確に示されています。
- 競合分析では、日本語のみに対応している既存サービスを網羅的に比較し、自社の優位性を強調しています。特に、「○○」「○○」という特徴が評価されました。
- 差別化の明確さ
- 自社の優位性として、文化的背景に対応したサポート体制や、金融機関との連携による資金調達力が具体的に示され、模倣困難なビジネスモデルである点が強調されています。
(3)事業の実現可能性
- 実施体制の整備
- プロジェクトチームの編成や、専門家の採用計画など、実施体制が明確に整備されています。
- ITシステムの開発や運用について、既存のシステム開発パートナーと協力することで実現性を高めています。
- 財務基盤の安定性
- 補助金以外に○○銀行からの融資が確保されており、資金面でのリスクが低いことが評価されました。
- 財務状況の安定性と補助事業の実施能力が具体的な数値で示されています。
- スケジュールと課題解決の計画性
- 事業スケジュールは、初期開発、パイロット運用、本格展開と段階的に計画され、課題ごとの解決方法が具体的に提示されています。
(4)公的補助の必要性
- 経済波及効果
- 本事業が雇用創出だけでなく、地域経済の活性化にもつながることが評価されています。
- 特に○○県内の中小企業と連携し、地域社会に定着させる仕組みが地域経済への波及効果として強調されています。
- 費用対効果
- 補助金の活用により、サービスの構築と展開が加速し、5年間で初期投資を回収可能である点が具体的に示されています。
- 補助金がもたらす成果(利益、雇用、地域経済への貢献)が費用対効果の高いものであることが評価されました。
(5)政策面
- デジタル技術の活用
- オンラインプラットフォームを活用したサービス提供は、ポストコロナ時代の非接触型ビジネスの促進に寄与すると評価されました。
- 特に、デジタル技術を用いたシステムが、日本国内では革新的な取り組みとされています。
- 地域特性の活用
- 多文化共生が求められる地域特性を生かし、地域の課題解決に寄与する内容が政策目標と合致しています。
このように、本計画書は審査基準に沿って具体的かつ実現可能性の高い内容が盛り込まれており、採択に結びついたと考えられます。さらに詳細な点について補足が必要であれば、ぜひお知らせください。
いかがでしたでしょうか?
本事業計画は、拡大中の市場でしたが、ターゲットがそのままでは競合が多く、事業の実現性が低かったものの、ターゲットを変更し、さらにその中でもターゲットを絞り、ペルソナ設定を明確にすることで、事業の実現性が評価されたものだと考えています。
財務状況に不安があったものの、金融機関からのバックアップが手厚く、財務状況の課題を解決できると判断されたと考えています。以前、採択されるコツは、これまでの事業の実績や経験が重要だと記載しました。この事業者様は、「金融機関との強い関係性の構築」という強みを保有しており、それはこれまでの事業の実績が金融機関に認められたうえで、社長が金融機関との信頼関係を構築することを重視したからだと考えています。
参考になれば幸いです。