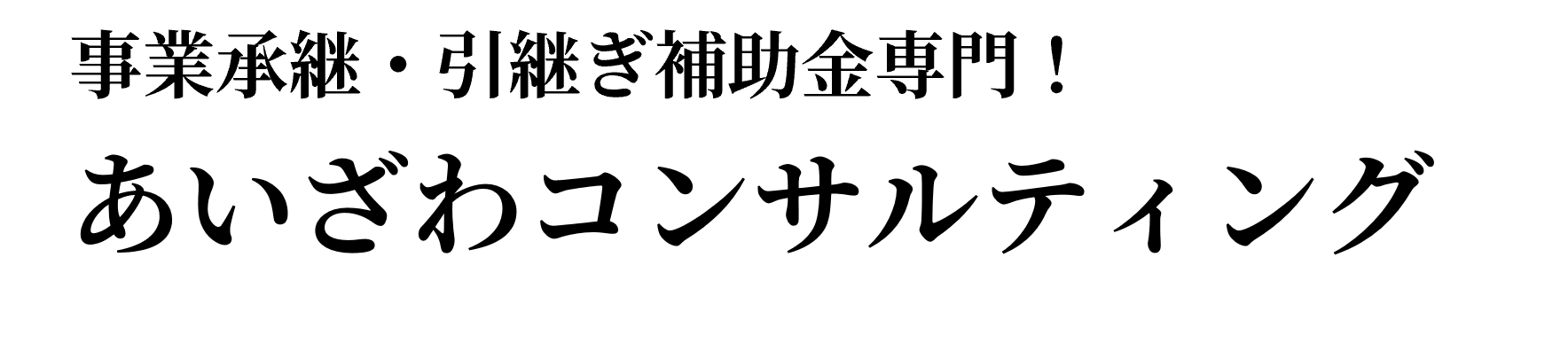いつもお世話になっております。あいざわコンサルティング、中小企業診断士の相澤和彦です。
16次ものづくり補助金で支援させていただいた事業者様の事業計画書が採択されました。
16次ものづくり補助金は、2件申請し、2件とも採択されました。この時は100%の採択率を誇っていた頃ですが、この1か月後、事業再構築補助金11回の採択発表があり、初めて不採択の事業計画書を出してしまいます。
私の得意分野の業種ですが、製造業、建設業のほか、自動車整備業があります。この事業計画書は、個人事業主の自動車整備業者様ですが、これまで手作業で行っていた板金塗装作業の省力化省人化を図ると言う内容で採択されました。また、自動車整備業界では、これまでの油性塗料から環境に優しい水性塗料への移行が始まっています。環境への負担を減らすと言う内容でもあったため、採択につながったと考えております。
採択された事業者様の事業計画書をChatGPTで分析してみました。
「○○」の事業計画書について、審査項目と照らし合わせる形で採択理由を整理してみます。以下に主な理由を示します。
(1) 補助対象事業としての適格性
ポイント
この事業計画では、「付加価値額の年率平均3%以上の増加」という基準を達成する具体的な計画が示されていました。以下のような点が審査基準を満たしたと考えられます:
- 生産性向上の明確な取り組み
- 新しい設備(フレーム修正機、塗装ブース、水性塗料対応の乾燥機)の導入により、外注していた作業を内製化し、コスト削減を実現。
- 作業効率向上により施工台数が増加し、売上増加につながることを具体的に数値で示しています(例: 年間施工台数150台から250台に増加予定)。
- 中長期計画の具体性
- 3~5年後の売上高やコスト削減効果が明確に記載されており、付加価値の増加率が計画的かつ現実的であることが評価されました。
評価のポイント
補助事業の効果を数値化し、目標達成の道筋を具体的に説明していることが、適格性の高さとして評価されたと考えられます。
(2) 技術面
① 革新性の評価
- 環境対応技術:水性塗料を使用することで、環境負荷を低減するとともに、法規制への対応力を高めています。これにより「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化」に沿った取り組みと認識されました。
- 品質向上:塗装の均一性と仕上がりの精度が向上する設備の導入により、競争力が大幅に強化される点も評価されました。
② 課題解決の明確化
- 外注していたフレーム修正や塗装工程を内製化することで、外注費削減(10分の1への削減)を実現し、利益率向上に寄与。
- 「短納期対応」や「品質の安定性」を実現する設備を導入し、顧客ニーズを満たす計画を具体的に提示。
③ 優位性の証明
- 地域内での競合分析を行い、新設備の導入による差別化ポイント(短納期・高品質)を明確化。
- 技術面で他社より優位性を持つ具体的な数値目標を示しています。
(3) 事業化面
① 実施体制の構築
- 新しい設備を活用するための技術者育成計画が明確に示されています。たとえば、地元の若年層を採用し、専用の研修プログラムを設けることで、技術継承を図る取り組みが評価されました。
- 協業先との安定的な取引関係が記載されており、継続的な案件受注が見込まれることが事業化の確実性を高めています。
② 市場ニーズへの対応
- 地域の顧客層を対象にしたマーケティング戦略を示し、短納期・高品質のニーズを取り込む計画が評価されました。
③ 費用対効果
- 設備導入によるコスト削減(外注費の削減)、施工台数増加による売上増加が具体的に数値化されており、費用対効果が高い点が審査員の評価ポイントとなったと考えられます。
(4) 政策面
① 地域経済への貢献
- 地域の高齢化や人口減少という課題に対応するため、新工場を拠点に地域雇用の創出を図る点が評価されました。
- 地元の専門学校との連携による若手技術者の育成が、地域全体の人材不足解消にもつながる取り組みとして高く評価されています。
② 環境配慮と持続可能性
- 環境に配慮した水性塗料の導入や、省エネ型乾燥機の採用が、政策的な重点項目(環境負荷低減)に合致しており、加点対象となったと考えられます。
③ ニッチ市場での差別化
- 高品質・短納期という特徴を活かし、地域内で競争力を確保しつつ、将来的には他地域への展開も視野に入れた計画が評価されました。
(5) その他(グリーン枠や賃上げ枠への対応)
- グリーン枠:水性塗料や省エネ設備による炭素生産性向上が具体的に示されており、温室効果ガスの削減が期待される内容となっています。
- 賃上げ枠:従業員への還元として賃上げ計画や技術者育成が盛り込まれており、持続可能な経営が評価されています。
総合的な評価
審査項目に基づき、この事業計画は以下の理由で高く評価され、採択に至ったと考えられます:
- 具体的かつ達成可能な中長期計画が記載されていること。
- 環境負荷低減や地域経済への貢献など、政策的な目標に合致していること。
- 設備投資による生産性向上が明確であり、費用対効果が高いこと。
- 実施体制や顧客ニーズへの対応がしっかりと組み込まれていること。
この事例は、補助金申請において重要なポイントを網羅しており、同様の取り組みを検討している事業者にとって参考となるでしょう。
いかがでしたでしょうか?
確かにChatGPTは便利ですが、事業計画書に使うことはしません。このような分析に使用することに留めています。AIを使った事業計画書は画一的な印象となってしまい、事業計画書の作成に必要な時間は減りますが、採択の確率が減ってしまう原因となります。
また、AIで文章を作成した際、確認作業を怠りがちになってしまいます。まず、AIが「高い正確性」や「効率性」を持つという認識が広まり、過度な信頼を抱いてしまうことが挙げられると考えています。特に、AIが専門的な知識や洗練された言葉遣いを用いる場合、人間が容易に間違いを見抜けないと感じることが心理的に影響し、確認を省略することにつながります。
また、AIの文章作成は手間がかからず短時間で結果を得られるため、「効率性」を優先し、本来必要な確認作業を軽視してしまう傾向があります。さらに、AIを「権威」や「無謬の存在」として捉える場合、人間がチェックする必要性を感じにくくなることも要因の一つです。
このような心理を克服するには、AIの作成する文章も「サポートツール」に過ぎないと再認識し、最終的な責任は人間にあることを意識することが重要です。