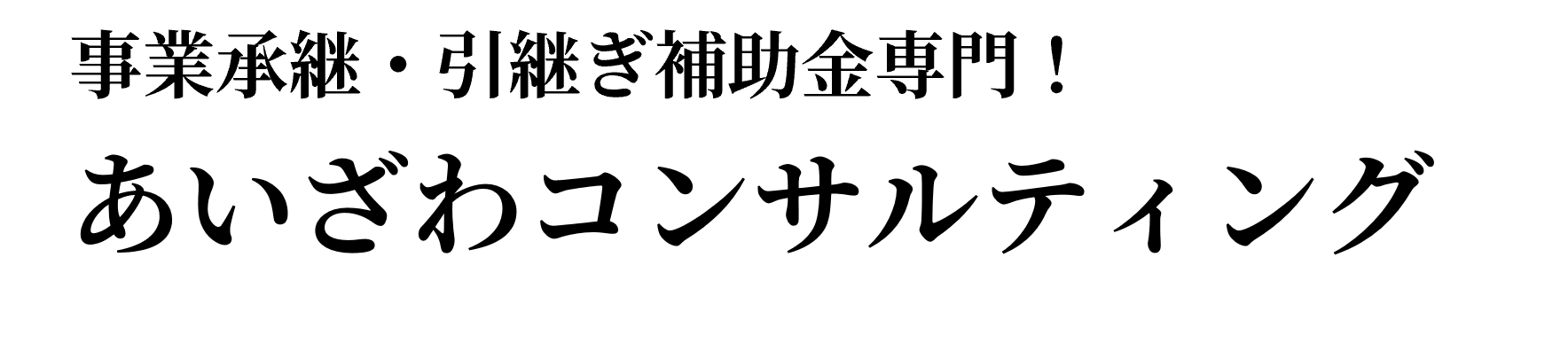はじめに
いつもお世話になっております。あいざわコンサルティング、中小企業診断士の相澤和彦です。
16次ものづくり補助金で支援させていただいた事業者様の事業計画書が採択されました。
16次ものづくり補助金は、2件申請し、2件とも採択されました。この時は100%の採択率を誇っていた頃ですが、この1か月後、事業再構築補助金11回の採択発表があり、初めて不採択の事業計画書を出してしまいます。
私の得意分野の業種ですが、製造業、建設業、自動車整備業、そして、運送業や倉庫業があります。この事業計画書は、運送業と倉庫業ですが、新たな新事業を図ると言う内容で採択されました。
前回に引き続き、採択された事業者様の事業計画書をChatGPTで分析してみました。補助金申請を成功させるためのポイントは、申請内容が審査項目をしっかり満たし、事業計画の説得力があることです。今回は、実際の事業計画を参考に、補助金が採択された理由を審査項目ごとに分析します。企業名などの具体的な情報は非公開としていますが、どのように計画が評価されたかを明らかにします。
審査項目ごとの分析
(1)補助対象事業としての適格性
本事業は「○○効率化システムの開発による○○システム提供の三位一体サービス」という明確な取り組みを掲げています。補助金の基本要件である「付加価値額の年率平均3%以上の増加」を5年間で16.44%と大きく上回る計画が示されています。また、事業のスケジュールが詳細かつ現実的であることもポイントです。
(2)技術面
- 新規性と革新性
物流効率化システムの導入により、○○の防止、○○対応、自動化された顧客対応など、競合他社にはない独自の機能を持つことが革新性として評価されました。このシステムは、特定ものづくり基盤技術高度化指針に基づく革新的技術の導入とみなされます。 - 課題解決の具体性
紙ベースの○○からリアルタイム共有可能なシステムへの移行により、リスクを大幅に低減。さらに、多国語対応で海外市場も視野に入れています。 - 技術力
システム開発の経験を持つ企業との提携や、自社内に専門知見を有する担当者がいることも、技術面での信頼性を高めています。
(3)事業化面
- 実現可能性
具体的な市場調査に基づき、1年目に5社、5年目には16社のクライアント獲得を目標としており、既に1年目の顧客を確保済みです。また、資金調達については、銀行借入と代表者の役員借入で安定した財務計画を提示しています。 - 収益性と費用対効果
新システム導入により経費削減と効率化を図り、3年以内に初期投資を回収できる計画です。これにより、補助金の費用対効果も高いと評価されています。
(4)政策面
- 地域経済への貢献
事業実施による雇用創出や、取引先の事業拡大を通じた地域経済の活性化が期待されています。また、物流効率化により地域企業の競争力を高める点も加点対象です。 - イノベーション性
○○業務全般を包括的に効率化するシステムは、他社にない独自のビジネスモデルであり、日本全体の経済構造の転換を促す可能性が評価されました。
採択理由のまとめ
補助金採択の理由として以下の点が挙げられます:
- 明確かつ達成可能な事業計画:目標が具体的で現実的。
- 革新的な技術の導入:他社との差別化を図る先端的なシステム。
- 地域社会や経済への波及効果:雇用拡大や地域活性化への寄与。
- 費用対効果の高さ:短期間での投資回収計画。
おわりに
いかがでしたでしょうか?
確かにChatGPTは便利ですが、事業計画書に使うことはしません。このような分析に使用することに留めています。AIを使った事業計画書は画一的な印象となってしまい、事業計画書の作成に必要な時間は減りますが、採択の確率が減ってしまう原因となります。
また、AIで文章を作成した際、確認作業を怠りがちになってしまいます。まず、AIが「高い正確性」や「効率性」を持つという認識が広まり、過度な信頼を抱いてしまうことが挙げられると考えています。特に、AIが専門的な知識や洗練された言葉遣いを用いる場合、人間が容易に間違いを見抜けないと感じることが心理的に影響し、確認を省略することにつながります。
また、AIの文章作成は手間がかからず短時間で結果を得られるため、「効率性」を優先し、本来必要な確認作業を軽視してしまう傾向があります。さらに、AIを「権威」や「無謬の存在」として捉える場合、人間がチェックする必要性を感じにくくなることも要因の一つです。
このような心理を克服するには、AIの作成する文章も「サポートツール」に過ぎないと再認識し、最終的な責任は人間にあることを意識することが重要です。
補助金採択を目指す企業にとって、本記事で紹介した事例は非常に参考になるはずです。審査項目に沿った計画立案と明確なビジョンを持つことで、採択の可能性を高めることができます。自社の計画を見直し、補助金申請に挑戦してみてはいかがでしょうか?